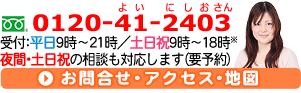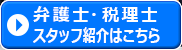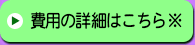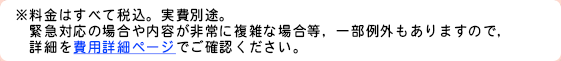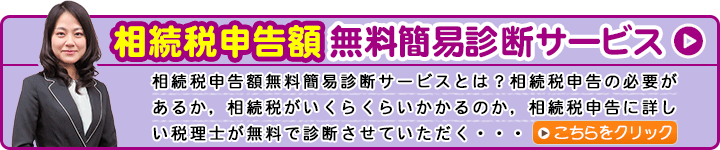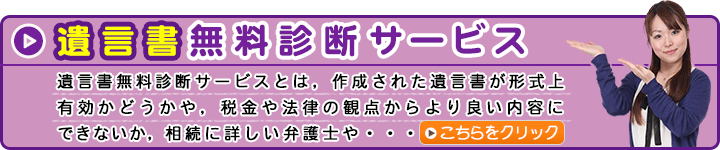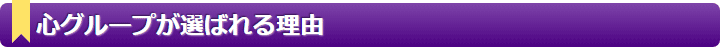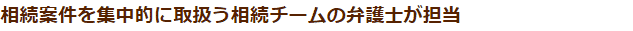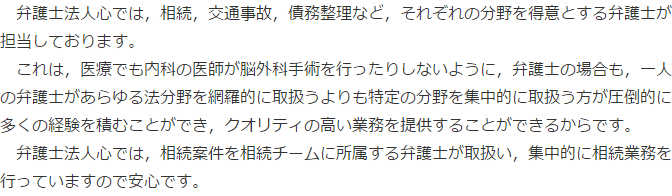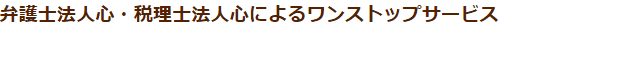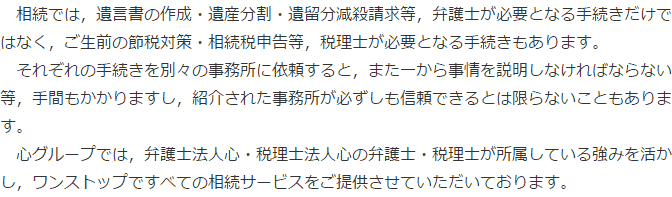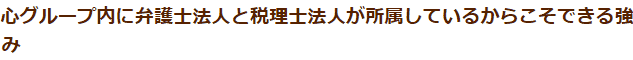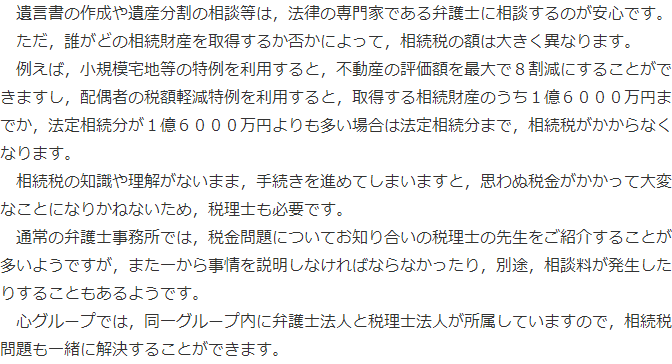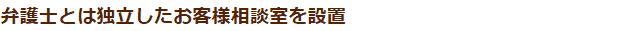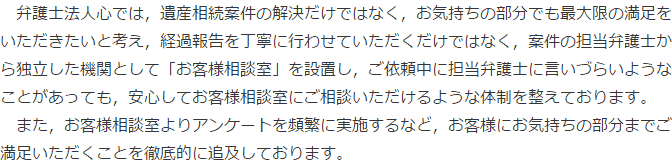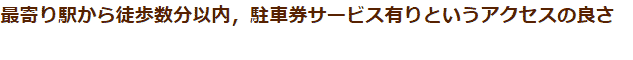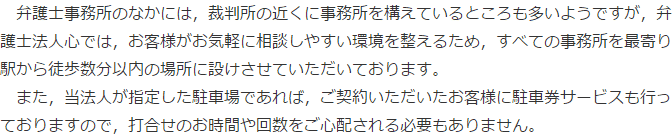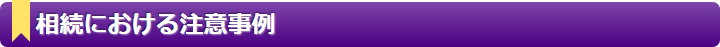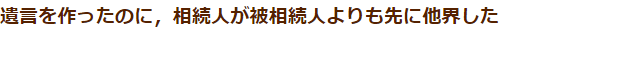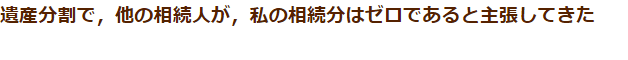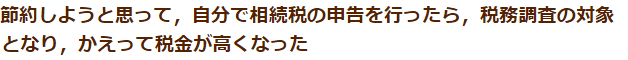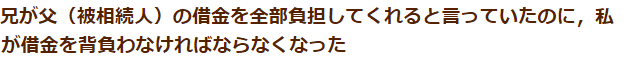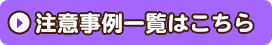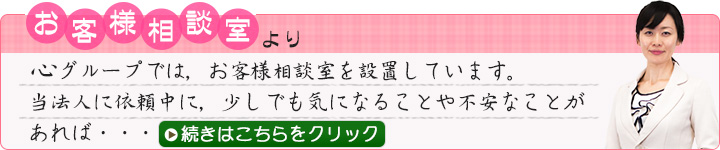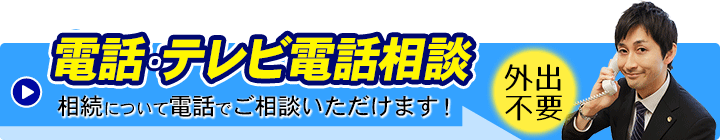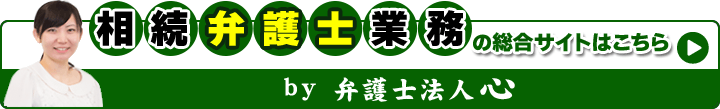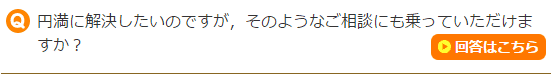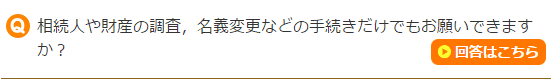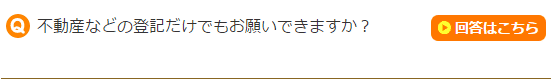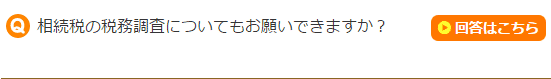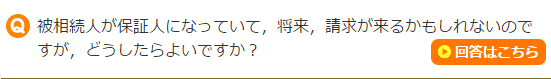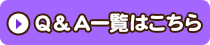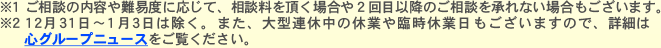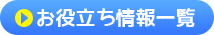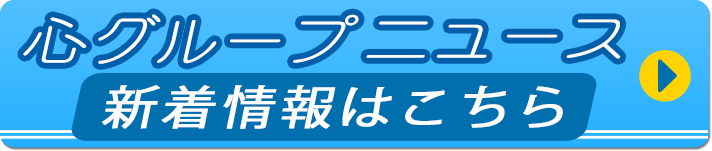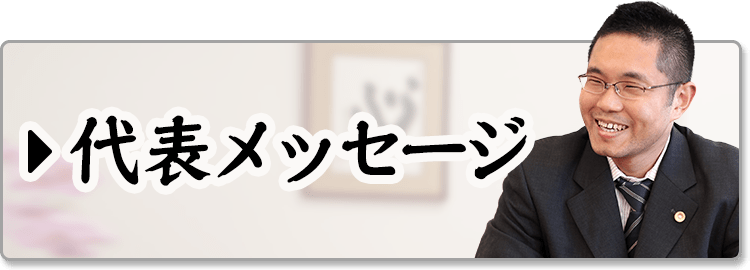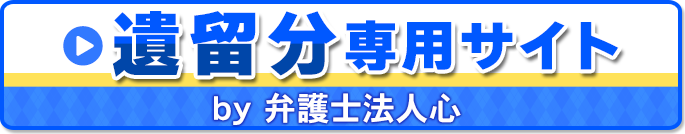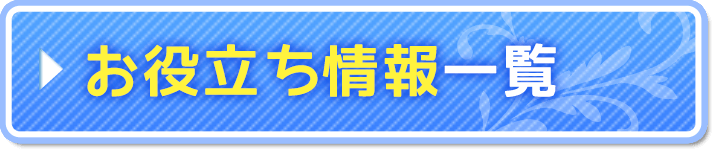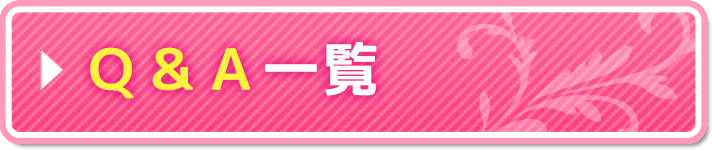業務内容
蒲田で相続でお困りの方へ
私たちは、幅広い専門知識が求められる相続をトータルサポートできる体制を整えています。その他にも強みや特徴がありますので、こちらをご覧ください。
注意すべき事例
相続における不測の事態に備えるためにも、相続で注意すべき点を知っておくことは大切です。注意事例をいくつかご紹介しておりますので、蒲田の方も参考にしてください。
サイト内更新情報(Pick up)
2026年2月12日
手続き
株式などの有価証券を相続する手続き
株式など有価証券の相続手続きとは、基本的に何か具体的な物品の移動があるわけではなく、被相続人名義の上場株式の名義の変更を行うことになります。株式は原則電子化されている・・・
続きはこちら
2026年1月9日
相続放棄
相続放棄をすると死亡退職金は受け取れないのか
相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切相続することができなくなってしまいま・・・
続きはこちら
2025年12月5日
遺留分
遺留分の計算はどのように行うか
遺留分は、相続人に認められる最低限の相続権の事を指します。例えば、被相続人A、その子であるB、Cがいたとして、被相続人のAが、子のBに対して、自分の財産の全てを相続・・・
続きはこちら
2025年11月28日
相続登記
不動産を相続した場合の相続登記の流れ
被相続人がお亡くなりになって、その方が不動産をお持ちの場合、不動産登記の名義を被相続人から移転する必要があります。相続登記については、大きく分けて以下の3つの基本・・・
続きはこちら
更新情報のご案内
サイト内の情報を随時更新しており、更新情報をこちらからご確認いただけます。
事務所のご案内
こちらから、事務所所在地をご確認いただけます。お問合せ先の情報なども併せてご確認いただけますので、相談をお考えの方はご参照ください。
相続の相談をしてから解決までにかかる時間
1 解決までにかかる時間はケースによって大きく異なる

結論から申し上げますと、相続開始後に行わなければならない手続きや問題の解決にかかる時間は、相続財産の内容や相続人の状況等によって大きく異なります。
相続が発生し、専門家に相談をした後に行わなければならない代表的なものとしては次のものが挙げられます。
①遺産分割協議書の作成
②預貯金の解約
③相続税申告・納付
④相続登記
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。
多くの相続手続きにおいて必要となる書類です。
なお、相続人が1人しかいない場合には、遺産分割協議書の作成は必要ありません。
遺産分割協議書の作成にかかる時間は、相続人の間で遺産分割に関する争いがない場合と、争いに発展してしまった場合とで大きく変わります。
まず、いずれにも共通して必要な作業として、相続人調査と相続財産調査があります。
遺産分割協議は相続人全員で行わないと無効になってしまうため、戸籍謄本類を収集して相続人を確定させます。
戸籍謄本類の収集には、一般的には1~2か月程度を要します。
相続人調査と並行して、相続財産調査を進めることができ、この調査は、財産の種類や、残っている資料の状況にもよりますが、概ね1~2か月程度の期間を要します。
相続人調査と相続財産調査を終え、話し合いで遺産分割の内容が決まったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印をします。
遺産分割協議書の作成には、通常約1か月かかります。
遺産分割協議がまとまらず、争いになってしまった場合には、相続人の間での話し合いで遺産分割協議が成立するケースであっても遺産分割協議書を作成するまでには6か月~1年かかります。
当事者同士での話し合いでの解決が難しく、遺産分割調停・審判を行わざるを得なくなった場合、1年~2年程度の時間が必要になると考えられます。
遺産分割調停や審判になった場合、遺産分割協議書の代わりに調停調書または審判書を取得することになります。
3 預金・貯金の解約
金融機関等で被相続人の預金・貯金を解約し払い戻しを受ける場合、基本的には遺産分割協議書が必要となります。
預金・貯金の解約は、金融機関等の窓口で必要な書類の提出等を行ってから1か月程度で完了することが多いです。
金融機関ごとに手続きを行わなければいけませんので、複数の金融機関に口座があるような場合は、その分手間がかかります。
4 相続税申告・納付
被相続人の財産が一定の評価額を超える場合には、相続税の申告と納付が必要となることがあります。
相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日(一般的には、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に行う必要があります。
相続税申告をする際も、基本的には遺産分割協議が完了している必要があります。
各相続人に課せられる相続税の金額は、取得した相続財産の評価額によって算定されるためです。
相続税申告の準備の際には相続財産の評価が必要となりますので、ある程度は相続財産調査と並行して進められます。
土地の評価などについては、複雑な計算や調査が必要となることがあるため、時間を要することがあります。
相続財産調査や遺産分割協議と並行して相続税申告の準備を進めた場合には、遺産分割協議書作成後、申告書を税務署に提出するまでに1~2か月程度かかります。
なお、遺産分割の話し合いがまとまらず、相続税の申告期限までに遺産分割協議書の作成ができない場合には、一旦法定相続割合で分割をしたと仮定して申告・納税をすることがあります(いわゆる「未分割申告」)。
5 相続登記
令和6年4月より相続登記は義務化されましたので、相続財産に不動産が含まれている場合には注意が必要です。
相続登記をするためには遺産分割協議書が必要となりますが、相続財産調査等と並行して準備を進めることもできます。
相続登記は、管轄の法務局に申請をしてから相続人への名義変更が完了するまで、1か月程度かかります。
不動産の名義変更をしないと、不動産を売却することなどができません。
もし、不動産を売却して相続税の納税資金にしようとお考えの場合は、迅速な手続きが求められます。
相続のご相談をお考えの方へ
ご相談をお考えの方に向けて、様々な情報をお役立ち情報として掲載しておりますので、ご一読ください。少しでも参考にしていただけますと幸いです。