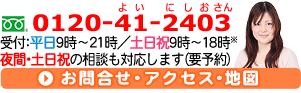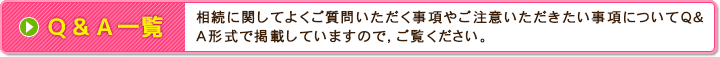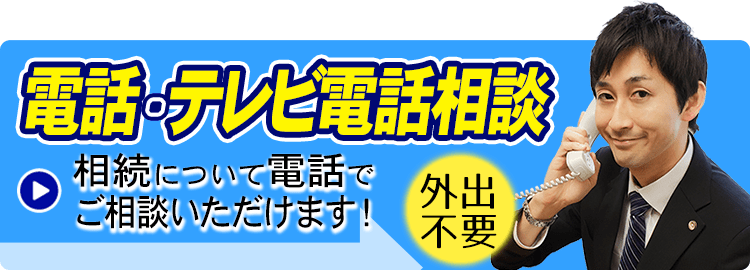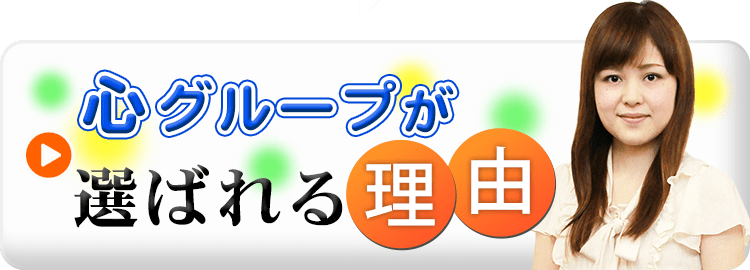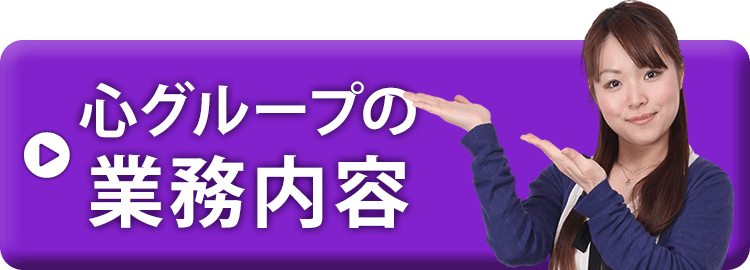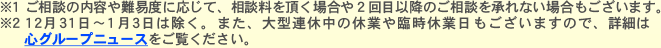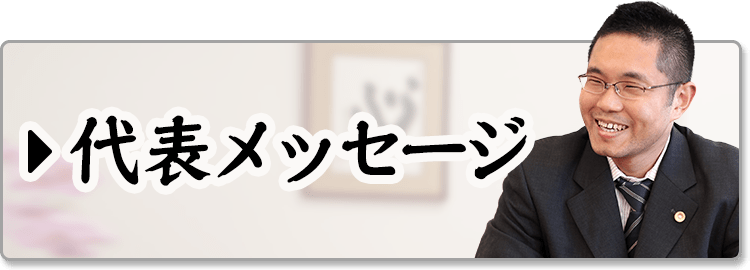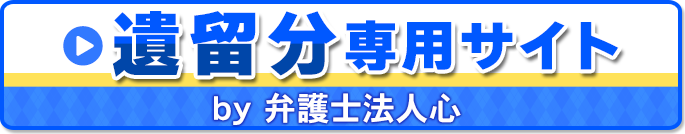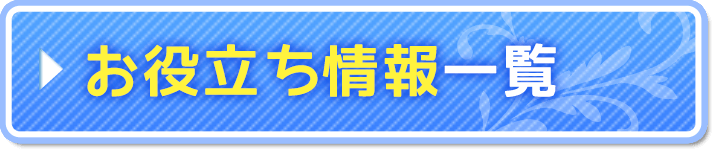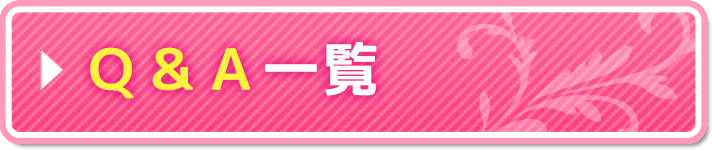預貯金の仮払い制度の利用方法
1 預貯金の仮払い制度とは?
預貯金の仮払い制度は、遺産分割協議成立前に、一定の条件の下で、各金融機関に被相続人の預貯金の払戻しを請求できる制度です。
預貯金については、金融機関が相続人からの連絡や、被相続人が著名な方であればお悔やみ記事等により、被相続人がお亡くなりになったことを知った場合、被相続人名義の預貯金口座を凍結します。
預貯金は、最高裁判所の判断が変わり、遺産分割協議の対象財産であるとされました。
そのため、預貯金は、被相続人名義の預貯金口座の凍結後は、遺産分割協議により、相続人の誰が、どの預貯金を取得するということが決まって初めて処分(引出・解約)することができることが原則となります。
被相続人の年金等で生活していた配偶者等は、緊急に生活費や葬儀費用等で預貯金を利用しようとしても、遺産分割協議が成立するまでは預貯金の利用ができないということになり、配偶者等の生活に支障が生じます。
そこで、遺産分割協議が成立して初めて処分できるという原則を一部修正し、一定の条件の下で、各相続人が、各金融機関に被相続人の預貯金の払戻しを請求できるという預貯金の仮払い制度が、令和元年7月1日から施行された民法909条の2に設けられました。
2 利用方法について
⑴ 限度額について
預貯金の仮払い制度は、遺産分割協議の成立がなく、また、家庭裁判所の関与もなく利用できる簡易な手続きです。
そのため、同制度を利用して請求できる金額については、以下の2つの限度内である必要があります。
① 相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分=単独で払戻しをすることができる額
② 同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額の150万円を限度
例えば、法定相続人が子供2人(甲、乙)であり、相続開始時の預貯金債権額がA銀行に2000万円(普通預金)、B銀行に250万円(普通預金)、C銀行に150万円(普通預金)の合計2400万円ある場合で説明します。
上記①の限度額は、上記の例でいうと、甲、乙が各自400万円(2400万円×1/3×法定相続分1/2)となります。
もっとも、上記②の限度額がありますので、甲がこの制度を利用する場合、A銀行やB銀行に対しては150万円ずつしか請求できないということになります。
⑵ 必要書類について
一般的には、以下の書類が必要となりますが、各金融機関で取り扱いが異なることがありますので、実際の手続きの際には請求先の金融機関に確認することが必要です。
① 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(被相続人出生から死亡までの連続しているもの)
② 相続人前任の戸籍謄本または全部事項証明書
③ 預金の払戻しを希望する方の印鑑証明書
3 留意点について
預貯金の仮払い制度は、この制度を利用して預貯金の払戻しを受けると、その限度で遺産分割の全部または一部が行われたと法的に見なされてしまいます。
その結果、実は負債が資産を大きく上回っていたような場合、この仮払い制度を利用したことで、遺産を取得したことになり、その結果、相続放棄ができないおそれがあります。
そのため、仮払い制度利用に当たっては、資産、負債をよく調べてから行う必要があります。
4 相続手続きのことはご相談ください
預貯金の仮払い制度は、遺産分割協議の成立が不要な点で利用しやすい制度であり、限度額の範囲内の利用の場合には有用な制度といえます。
同制度を利用する場合など、相続手続きのことならお気軽にご相談ください。
不動産を相続した場合の相続登記の流れ お役立ち情報トップへ戻る