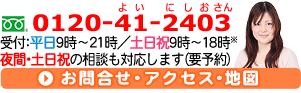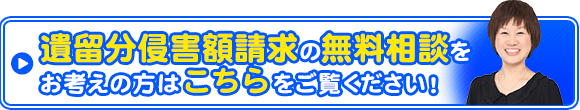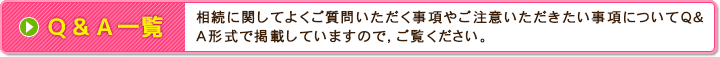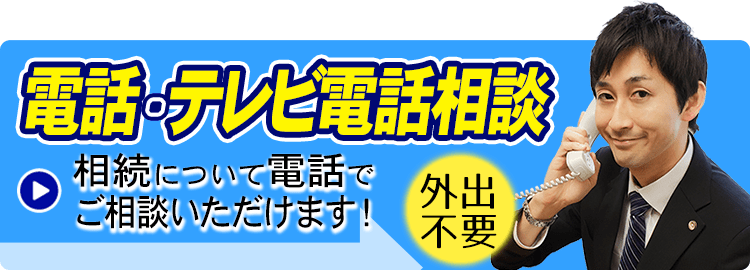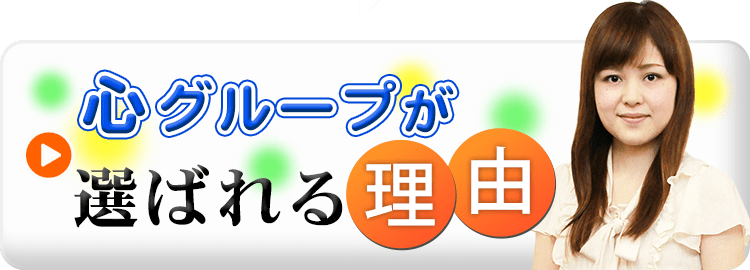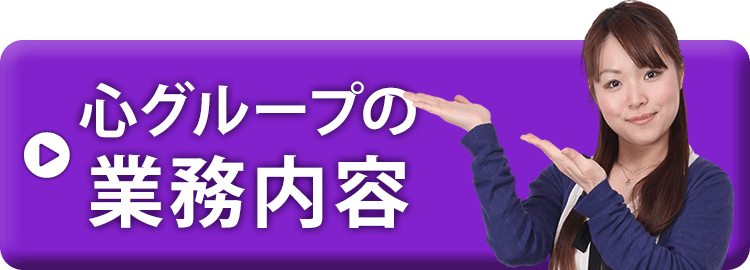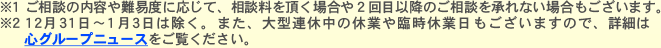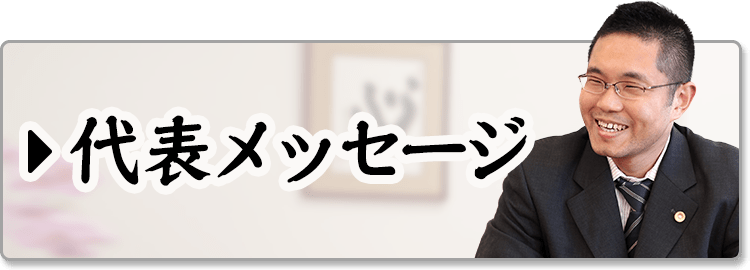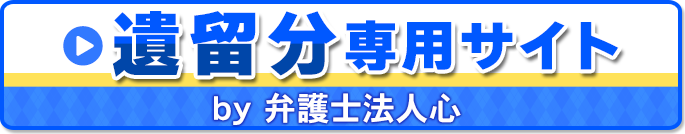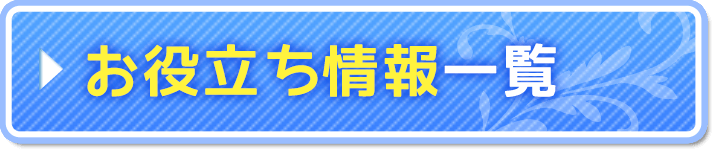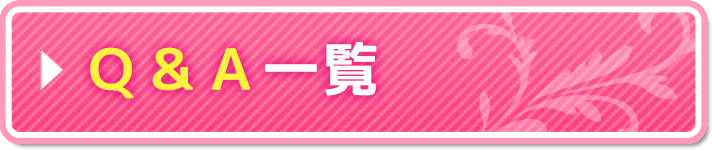遺留分の計算はどのように行うか
1 遺留分とは
遺留分は、相続人に認められる最低限の相続権の事を指します。
例えば、被相続人A、その子であるB、Cがいたとして、被相続人のAが、子のBに対して、自分の財産の全てを相続させるという遺言を残したとします。
この時、子のCは、Aの遺産を一切相続できないことになってしまうため、相続人の間に不公平が生じてしまいます。
この不公平を是正するため、CがBに対して、金銭の支払いを求めることができるようにした制度が遺留分なのです。
今回は、遺留分を侵害された場合に、どのように計算して遺留分の主張を行っていくのかについて解説していきます。
2 遺留分割合を求める
まず、総財産に対する遺留分の割合を計算していくことになります。
この遺留分割合については、法定相続分に、民法1042条1項各号に規定されている割合を乗じて求めることができます。
民法1042号1項は以下のとおりの規定となっております。
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
この規定を要約すると、配偶者や子供がいない場合の相続の際には、3分の1を、配偶者や子供が相続人になる場合には、2分の1を法定相続分に乗じて得た額(同条2項)が、遺留分割合となるということになります。
したがって、上述の、被相続人Aと、その子B、Cの相続に関する例で解説すると、Cの遺留分割合は、以下のようになります。
Cの遺留分割合=2分の1(Cの法定相続分)×2分の1(民法1042条1項2号の割合)=4分の1
3 財産の総額を確定する
遺留分割合を求めることができた場合には、その後に、財産総額を決定することになります。
この財産総額を算定する方法については、民法1043条1項に以下のように規定されています。
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
そのため、「被相続人の積極財産の価格」と「債務の価格」を求めることが重要です。
上述の例で、被相続人Aが土地建物3000万円、預貯金2000万円、債務1000万円を残していた場合には、以下のようになります。
Aの財産総額=3000万円+2000万円-1000万円=4000万円
4 遺留分額の計算
被相続人の財産総額が確定できた後には、財産総額に遺留分割合を乗じることで、遺留分の金額を求めることができます。
上述の例でいえば、以下となります。
Cの遺留分額=4000万円(Aの財産総額)×4分の1(Cの遺留分割合)=1000万円
したがって、CはBに対して1000万円の遺留分を請求することができるようになるのです。
相続放棄をすると死亡退職金は受け取れないのか 不動産を相続した場合の相続登記の流れ