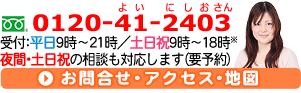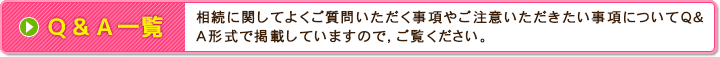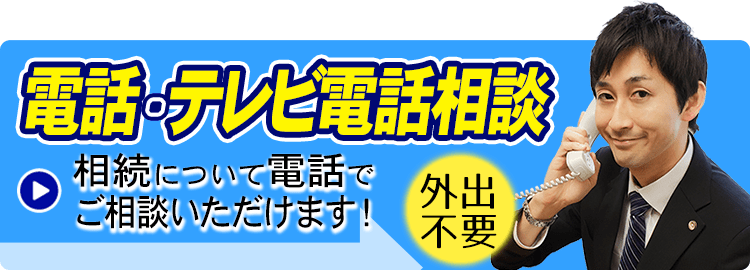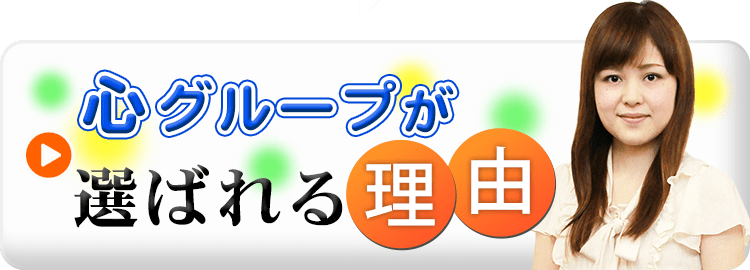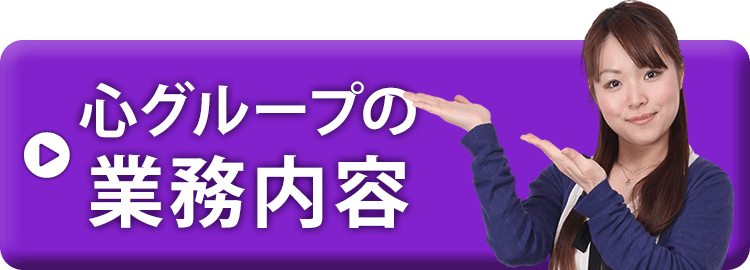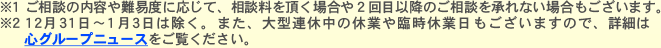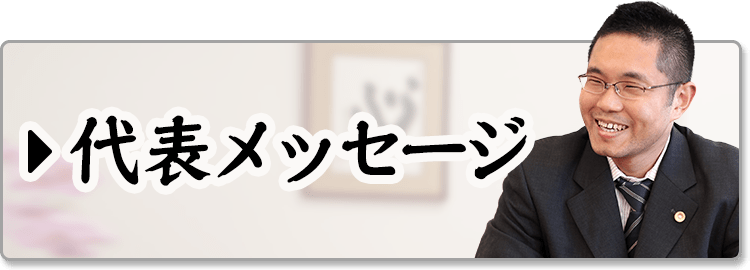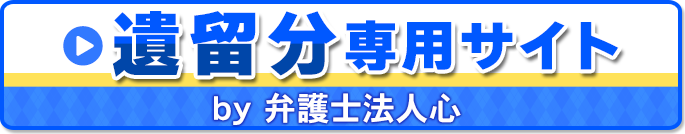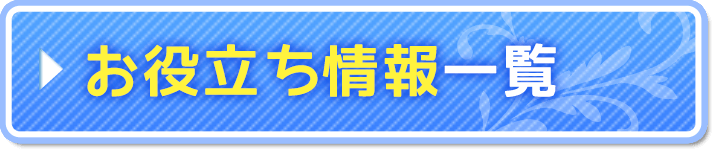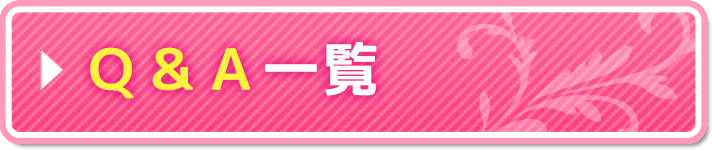株式などの有価証券を相続する手続き
1 上場株式の場合
株式など有価証券の相続手続きとは、基本的に何か具体的な物品の移動があるわけではなく、被相続人名義の上場株式の名義の変更を行うことになります。
株式は原則電子化されているため、上場株式を相続する場合は、被相続人名義の証券口座を有する証券会社(の担当者)に連絡を行い、名義変更と被相続人の証券口座から株式を相続する人の証券口座に移管する手続きを行うことになります。
つまり、上場株式を相続する人が証券口座を持っていない場合は、その人名義の証券口座を開設する必要があります。
その際に、移管先の口座は基本的に同種の口座である必要がありますので、被相続人が一般口座を持っていた場合は、一般口座を、被相続人が特定口座を持っていた場合は、特定口座を開設することになります。
なお、この口座の違いは、利用者が確定申告を行う場合は一般口座、金融機関が計算する場合は特定口座という違いになります。
2 非上場株式の場合
非上場株式の場合は、上場株式と異なり証券会社による管理は行われていません。
そのため、その株式を発行した会社に対し、直接相続手続きを依頼する必要があります。
具体的には、その株式を発行した会社に対し、株主名簿の書換えの請求を行い、被相続人名義から相続人名義に書き換えを行うことになります。
例外的に、株主名簿管理人がその発行会社ではなく、信託銀行などの第三者機関が株主名簿管理人となっている場合があります。
そのような場合は、当該株主名簿管理人に対して株主名簿の書換えの請求を行うことになります。
株主名簿管理については、原則株式発行会社の定款に定められていますので、手続きを行う場合は、株式発行会社へ問合せを行うことが重要です。
3 譲渡制限株式の場合
株式の中には、株式を売買等することについて、会社の許可を必要とする場合があります。
このような株式を「譲渡制限株式」といいます。
これについても、「相続」の場合は売買や贈与等とは違い、譲渡制限株式の例外として上述した上場株式、非上場株式の振り分けとおりの手続きを行うことで名義変更ができます。
ただし、譲渡制限株式について、会社は相続人に対して買取りを求めることができるように定款に定めを作ることができます。
そのような請求がなされた場合、相続人は株式の名義変更を受けることはできず、代わりにその株式の評価相当額の金銭等を取得することになります。
4 投資信託の場合
投資信託は、被相続人名義の商品を管理している金融機関に相続手続きを依頼することになります。
そのため、まずは被相続人の信託財産を管理している金融機関を調査して、問合せを行う必要があります。
金融機関ごとに取扱いは異なりますが、被相続人が利用していた金融機関と同じ金融機関への移管が一般的であるため、もし相続人が同一の金融機関に口座を持っていない場合は、口座開設を求められる場合があります。
5 有価証券を換金して相続する場合
相続人の誰も有価証券の運用を行っておらず、有価証券について金銭での受領を希望される場合があると思います。
しかし、その場合でも、有価証券は被相続人名義のままでは処分できません。
名義変更を行わないと、相続人であっても売却の手続きを行えませんので、有価証券について換金して相続することを希望したとしても、相続人の誰かに名義変更を行ったうえで、その名義変更を受けた人が売却の手続きや売却代金の分配等を行うことになります。
このとき、遺産分割協議書に売却代金の分配方法まで決めてしまえば、売却代金の分配時に贈与税等の税金が発生することは基本的になくなります。
逆にいえば、遺産分割協議に売却代金の取り扱い等にさだめがないと、分配時に税金が発生する危険があります。
そのため、換金を前提に有価証券を相続によって取得する場合は、事前に専門家に相談されることをおすすめします。
6 有価証券の手続きで忘れがちなもの(分配金)
有価証券の多くには、分配金が発生していることがあります。
この分配金については、分配金の決定が相続発生前か相続発生後なのかによって扱いが異なります。
相続発生日前に発生がきまっているもの(その年の株主総会日より後に相続開始日(被相続人の死亡日)がある場合など)は、その分配金についても遺産分割協議の対象ですので、遺産分割協議書で手続きを進める場合に、分配金の記載がないと、その部分について改めて遺産分割協議書を作らなければならないということがあります。
相続開始後に分配金の決定があった場合には、その分配金は遺産には含まれない相続人固有の財産となりますので、相続人個々人で手続きを行うことになります。
たいていの場合、配当の手続きについては被相続人名義で被相続人が生前登録していた住所地に必要な書類が届けられますので、その書類に従って行うことになります。