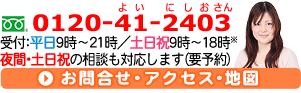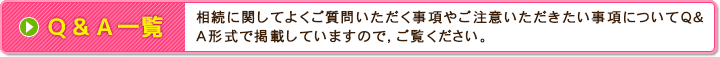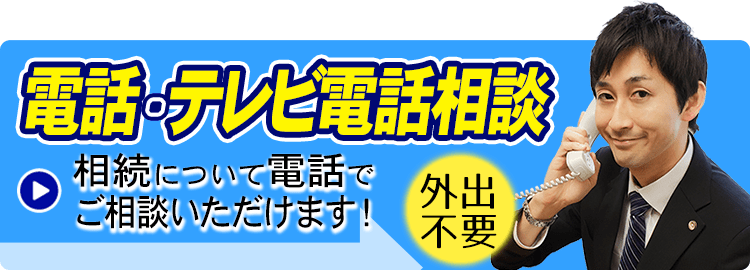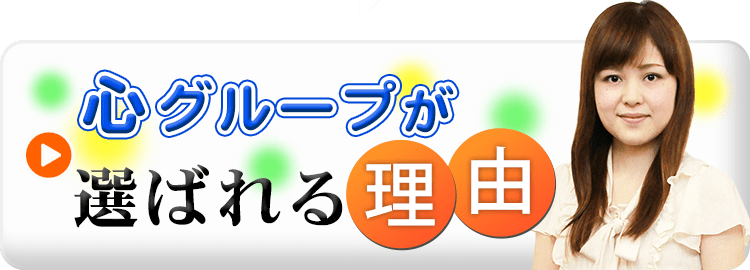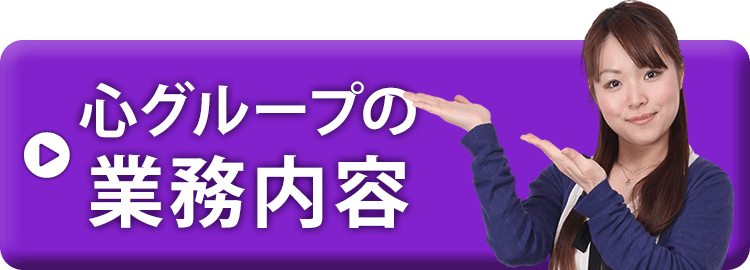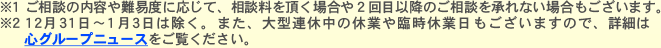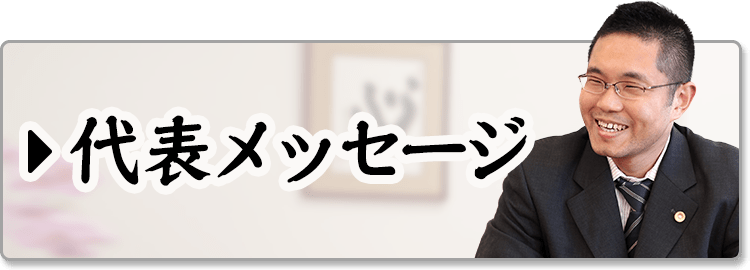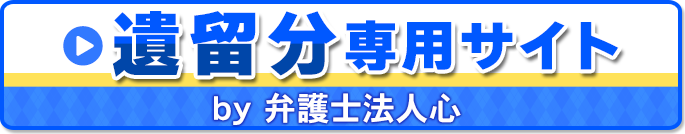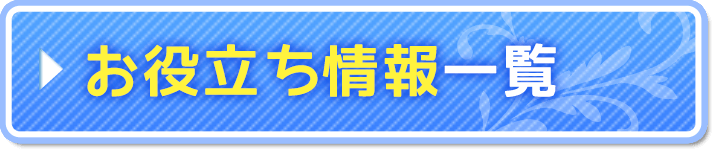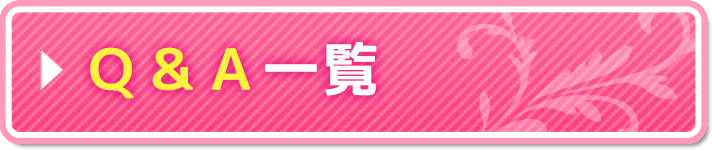不動産を相続した場合の相続登記の流れ
1 相続登記の基本パターン
被相続人がお亡くなりになって、その方が不動産をお持ちの場合、不動産登記の名義を被相続人から移転する必要があります。
相続登記については、大きく分けて以下の3つの基本パターンがあります。
① 遺産分割による相続登記
② 法定相続による相続登記
③ 遺言書による相続登記
2 遺産分割による相続登記
遺産分割による相続登記をするためには、原則として、相続人間で遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議は、相続人間の話し合いで決まるものですので、相続人間にあまり争いがない状況であれば、その協議で誰が不動産を相続するか等、決まった内容を基に遺産分割協議書案を作成し、その内容に相続人全員が納得したら、相続人各自が原則として自署し、自己の実印を押印して遺産分割協議書を作成します。
残念ながら、相続人間で仲が悪い等により、誰がどの遺産を取得するのかについて当事者同士の話し合いでは決まらないような場合には、家庭裁判所の調停手続き等の裁判手続きで遺産分割をする必要があります。
参考リンク:裁判所・遺産分割調停
争いの内容によっては専門的な知識が必要となりますので、弁護士に相談されることをおすすめします。
遺産分割協議書が作成できた場合、①遺産分割協議書原本、②相続人の印鑑証明書、③亡くなられた被相続人の出生までさかのぼった戸籍関係書類(改製原戸籍や除籍謄本等)、④収入印紙などの必要書類を添えて、不動産所有者の名義変更のための登記申請書を、その名義変更をしたい不動産の所在地を管轄する法務局に提出して、相続登記を行います。
提出方法は、①管轄法務局窓口に持ち込む方法、②管轄法務局に郵送で提出する方法、③オンラインにより提出する方法があります(参考リンク:法務局・不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方))。
もっとも、オンライン提出は、電子証明書を取得しなければならない等、一般の方にとっては面倒な手続きとなりますので、あまりお勧めはできません。
3 法定相続による登記
相続人間で話し合いをした結果、全ての遺産を法定相続分通りに分けることが決まった場合や、遺産分割協議がまとまらない場合にひとまず法定相続分通りの割合で不動産の名義変更登記を行う場合などで、法定相続による登記が行われることがあります。
遺産分割協議書が不要となるため、遺産分割による登記に比べるとシンプルな手続きとなります。
遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書という遺産分割の事実を証明する資料の提出が不要となる以外は、遺産分割の場合の相続登記の場合と同じ必要書類を添付して、不動産所有者の名義変更のための登記申請書を、その名義変更をしたい不動産の所在地を管轄する法務局に提出して、相続登記を行います。
4 遺言書による登記
遺言書による登記は、①遺言書が自筆証書遺言書なのか、②自筆証書遺言書保管制度を利用し、あるいは公正証書遺言書を利用したものかで手続きが大きく変わってきます。
自筆証書遺言書の場合には、家庭裁判所に遺言書の検認という手続きをとる必要があり、その検認を受けたという検認調書が相続登記の必要書類の一つとなります。
参考リンク:裁判所・遺言書の検認
他方で、自筆証書遺言保管制度を利用した場合や公正証書を利用した場合は、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要はありません。
公正証書遺言書以外の遺言書では、遺産の相続の内容に疑義がある等の問題があることもあり、そのような場合には、管轄の法務局に照会をする必要もあります。
照会した結果、その遺言書では相続登記ができないということもあり得ます。
そのため、公正証書遺言書以外で遺言書を作成する場合、その遺言書で相続登記ができるのかという点について、専門家にご相談頂くことが望ましいと思います。
遺留分の計算はどのように行うか 預貯金の仮払い制度の利用方法