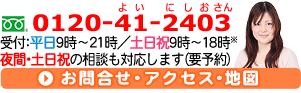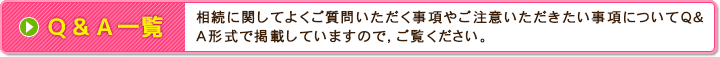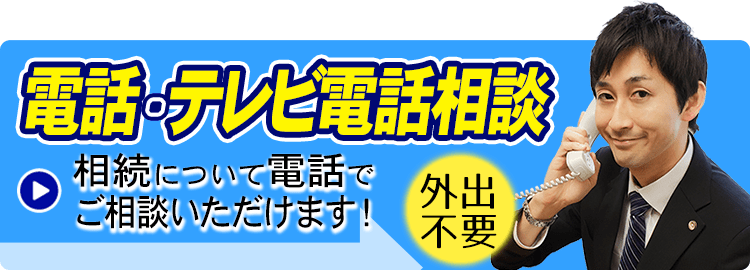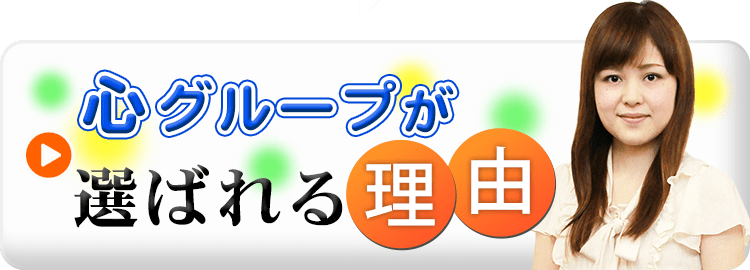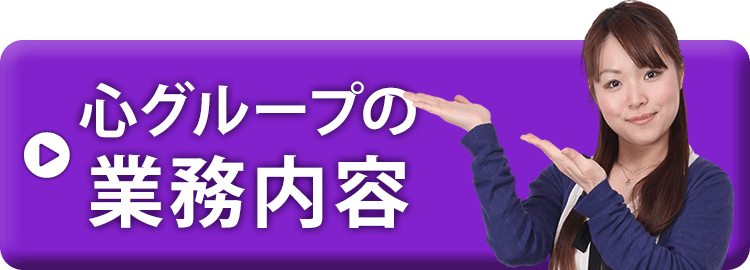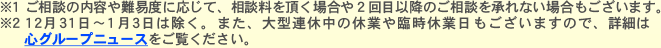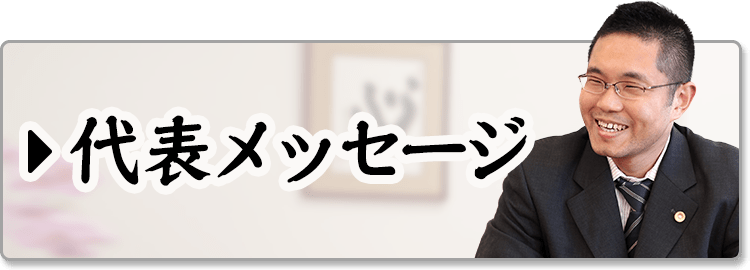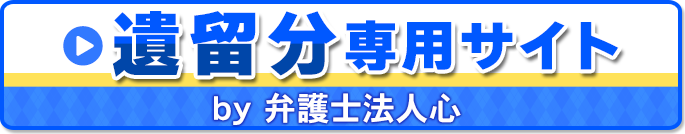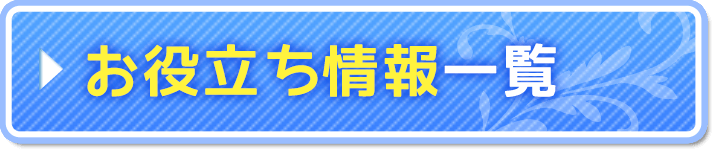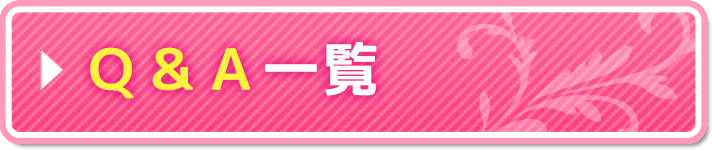銀行口座の相続手続きの流れ
1 銀行口座の相続手続きの必要性
銀行口座について、相続人のどなたかが銀行に被相続人が死亡したことを伝えた、あるいは被相続人が有名人等で銀行が死亡した事実を知った場合には、原則として銀行口座の入出金ができなくなり、銀行口座が凍結されます。
そのため、銀行口座凍結後、銀行口座を解約、銀行口座からの引出し等を行うためには、相続手続きを行う必要があります。
銀行口座の相続手続きの流れは、基本的には、①遺産としてどの銀行口座があるかの調査、②調査した銀行から残高証明書等を入手、③誰がどの銀行口座について取得するかの遺産分割協議、④解約、引出し等のための銀行への手続きという流れとなります。
以下、上記①から順にご説明いたします。
2 ①銀行口座の調査
①被相続人の作成した遺言書や生前のメモ等に、どの銀行に預金を有しているという記載がないか、②被相続人の自宅等に通帳や定期証書などがないかを確認して、被相続人が、どの銀行と取引があったのかを把握するようにします。
被相続人の自宅にある、カレンダーやボールペン等に銀行名などの記載があれば、取引があったかを確認するのも一つです。
3 ②残高証明書等の入手
調査の結果、ある銀行と取引があると思われる銀行に対し、被相続人が預金口座を有しているのか、有している場合、被相続人が亡くなった時点での残高証明書や、定期預金があれば被相続人死亡時の解約利息額計算書の提出を依頼します。
上記依頼には、被相続人死亡を示す除籍謄本や、請求者が相続人であることを示す戸籍謄本等の一定の書類が必要となりますので、金融機関に確認の上で、手続きを取って頂く必要があります。
最近は、預金口座の確認を依頼した場合、その金融機関の全ての被相続人の預金口座を開示してくれる例が多く、その開示により認識していなかった預金口座が見つかることがあります。
4 ③遺産分割協議
被相続人作成の遺言書がなく、誰がどの預金口座を相続するということが決まっていない場合には、銀行から取得した残高証明書等に基づき、全相続人の間で、誰がどの預金口座の預金を取得するのかについて遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議書の作成は、銀行口座の相続手続きで必ず必要というものではありまんが、誰がどの銀行の預金を取得するのかが明確に記載されている遺産分割協議書の場合、預金を取得しない方の銀行へ提出する相続届の署名、押印が省けますので、基本的には遺産分割協議書を作成することが望ましいと思います。
遺産分割協議書を作成する場合には、全相続人の署名、実印による押印や、印鑑証明書が必要となります。
5 ④解約、引出し等のための銀行への手続き
銀行口座の取得者が、遺産分割協議等により確定すると、銀行に対し、必要書類を提出して手続きを行います。
一般的には以下の書類が必要となりますが、各金融機関で取り扱いが異なることもありますので、事前に金融機関に問合せを頂いた方が、手続きがスムーズに進むかと思います。
① 金融機関所定の相続届(その金融機関の預金を取得される相続人の署名、実印の押印)
② 被相続人の死亡が確認できる除籍謄本
③ 遺言書がある場合は、遺言書(検認が必要な場合は、検認調書も)
④ 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合には、遺産分割協議書、被相続人及び相続人であることが分かる戸籍謄本一式、相続人全員の印鑑証明書(発行から6か月以内。金融機関によっては発行から3か月以内のものを要求するところもあります。)
6 銀行口座の相続手続きでお困りなら
銀行口座の相続手続きは、銀行口座の調査、残高証明書の取り付け、遺産分割協議書の作成、解約、引出し等のための銀行への手続きのための書類の収集など、手間暇がかかる手続きとなります。
そのため、銀行口座の相続手続に慣れた専門家に、銀行口座の相続手続きを依頼することも検討頂ければと思います。
株式などの有価証券を相続する手続き 相続放棄をすると死亡退職金は受け取れないのか